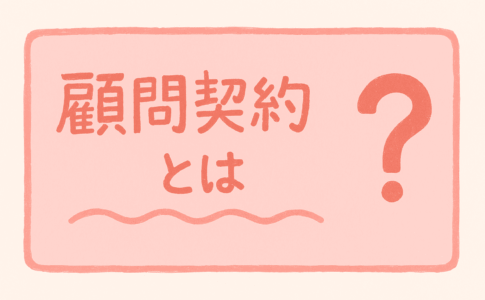融資審査で銀行が本当に知りたいこととは?
「決算書の数字は悪くないのに、なぜか融資審査で苦戦する」「銀行の担当者から追加資料ばかり求められる」。このような経験をお持ちの経営者の方は多いのではないでしょうか。
実は、銀行の融資審査では単に決算書の数字だけを見ているわけではありません。成長段階にある中小企業の融資審査においては、過去の事業実績を詳細に示す情報と将来の返済能力を裏付ける情報の両方を適切に提供することが、審査通過の決め手となります。
本記事では、銀行が融資審査で重視するポイントを踏まえ、審査に強い決算書の作り方と効果的な情報提供の方法について解説します。
融資審査成功の鍵:過去と将来の情報提供
銀行が求める2つの視点
銀行の融資審査では、大きく分けて2つの観点から企業を評価しています。
まず一つ目は「過去情報」、つまり実績の詳細です。これは決算書の数字の背景にある事業実態や、売上・利益の変動要因、そしてキャッシュフローの推移と安定性を見ています。
二つ目は「将来情報」で、事業計画の実現可能性や適切な借入先の選定、そして何より返済原資の確実性を重視します。
多くの中小企業が融資審査で躓く原因は、この2つの情報提供が不十分、またはバランスが悪いことにあります。特に「黒字だから大丈夫」という考えだけでは、銀行の不安を解消することはできません。
過去情報編:事業実態を見える化する決算書作成術
数字の裏側にあるストーリーを伝える
銀行が決算書を見る際、最も知りたいのは「なぜこの数字になったのか」という背景です。売上が増加した場合でも、それが一時的な特需なのか、営業努力の成果なのか、市場環境の変化なのかによって、評価は大きく異なります。
効果的な情報提供の3つのポイント
1. 売上構成の詳細な内訳
単に「売上高○○円」と記載するのではなく、もっと具体的な内訳を示すことが大切です。例えば、主要顧客別の売上構成比を明確にし、商品・サービス別の売上推移を時系列で示す。さらに新規顧客と既存顧客の比率や、地域別・部門別の業績まで開示すると、事業の実態がより鮮明に伝わります。
2. 費用の使途と効果の明確化
各費用項目についても、その内容と投資効果を丁寧に説明することが重要です。人件費であれば、単に金額を記載するだけでなく、増員の内訳や配置部署、そして期待される効果まで説明します。広告宣伝費なら、実施した施策と獲得顧客数を関連付けて示し、研究開発費については開発内容と事業化の見込みまで言及すると良いでしょう。
3. 月次データによる傾向分析
年次の数字だけでなく、月次推移を示すことで事業の安定性や成長性を証明できます。月別の売上高・利益の推移表を作成し、季節変動がある場合はその要因と対策を説明。さらに受注残高の推移も併せて示すことで、将来の売上見通しの確実性も伝えることができます。
スタートアップ企業における返済能力の証明方法
設立間もない企業や過去の実績が少ない場合は、別のアプローチで返済能力を示すことが重要です。
まず考えるべきは、返済リスクを軽減する裏付け資料の準備です。エクイティファイナンスの実績があればそれを前面に出し、まだの場合は具体的な計画書を作成します。場合によっては経営者個人の資産状況を開示することも検討し、親会社や提携先からの支援確約があればそれも活用しましょう。既存契約の継続性を示す書類も、安定性の証明になります。
さらに、将来性を示す具体的根拠も重要です。すでに締結済みの契約書や基本合意書があれば強力な武器になりますし、大手企業との取引実績は信用力の裏付けになります。特許や独自技術を持っている場合は、その説明資料も準備し、市場調査データと自社のポジショニングを明確に示すことで、成長可能性を具体的に伝えることができます。
業界特性による融資審査の違いを理解する
銀行の判断基準はシンプル:「返済できるか」
融資審査において、銀行が最終的に判断するのは「この企業は確実に返済できるか」という一点です。そのため、事業の見通しが立てやすい業界ほど融資審査に通りやすく、逆に将来予測が困難な業界は審査が厳しくなる傾向があります。
融資審査に通りやすい業界の特徴
KPIが明確で見通しが立てやすい業界の代表例として、人材紹介業があります。この業界は成約単価×成約数という明確な収益構造を持ち、過去実績から将来の売上予測が立てやすいという特徴があります。また、在庫リスクがなく、キャッシュフローが安定している点も銀行から評価されるポイントです。
同様にSES(システムエンジニアリングサービス)も、エンジニア数×稼働率×単価という計算式で収益が予測でき、契約期間が明確なため収益予測が容易です。人材さえ確保できれば売上が安定的に見込めるという点で、銀行からの信頼を得やすい業界といえます。
これらの業界は、過去のKPIデータを示すことで、銀行に対して「来月も再来月も、ほぼ確実にこれだけの売上が入る」ということを証明しやすいのです。
融資審査のハードルが高い業界
一方で、将来予測が困難な業界もあります。例えばSaaS(Software as a Service)は、初期は赤字が続くビジネスモデルで、解約率(チャーンレート)の予測が困難です。黒字化までの期間も読みにくく、銀行としては返済能力の判断が難しいのです。
新規事業やスタートアップ全般も同様で、過去実績がないため判断材料が少なく、市場の反応が未知数で競合の参入リスクも読めません。
ただし、重要な例外があります。エクイティファイナンスが可能な分野は、VCなどから資金調達ができることを示せれば、銀行も「最悪の場合でも返済原資は確保できる」と判断し、融資が通りやすくなります。
業界特性に応じた対策
見通しが立てにくい業界で融資を獲得するには、まず他の資金調達手段を明示することが重要です。エクイティファイナンスの実績や計画、補助金・助成金の採択実績、親会社やスポンサー企業からの支援などを具体的に示しましょう。
次にKPIの可視化に努めることです。SaaS企業であればMRR(月次経常収益)の推移や、顧客獲得コスト(CAC)と顧客生涯価値(LTV)の関係、コホート分析による解約率の詳細データなどを準備します。
さらにリスクヘッジ策も重要です。複数の収益源を確保していることや、最悪シナリオでの返済計画、経営者保証以外の担保提供なども検討に値します。
将来情報編:適切な借入先選定が融資成功率を高める
日本政策金融公庫と信用保証協会の使い分け
中小企業が利用できる主な公的融資には、日本政策金融公庫と信用保証協会付き融資があります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に応じて適切に選択することが重要です。
日本政策金融公庫は国が全額出資する金融機関による直接融資で、創業支援に積極的です。実績が少なくても利用しやすく、比較的低金利で返済期間も長期設定が可能。審査期間も比較的短いという特徴があります。
一方、信用保証協会付き融資は、金融機関からの融資に対して信用保証協会が保証する仕組みです。金融機関と保証協会の両方の審査が必要で、保証料が別途必要になりますが、金融機関のリスクが軽減されるため融資を受けやすくなります。また、地域の金融機関との関係構築にもつながるというメリットがあります。
成長段階に応じた資金調達戦略
創業期やアーリーステージでは、日本政策金融公庫の創業融資を軸に検討するのが基本です。併せて自治体の創業支援制度も活用し、何より事業計画書の作り込みに注力しましょう。
成長期やミドルステージに入ったら、信用保証協会付き融資を中心に資金調達を考えます。この段階では複数の金融機関との取引開始も検討し、月次決算体制の確立が信用力向上につながります。
安定期やレイターステージでは、プロパー融資への移行も視野に入ってきます。公的融資とプロパー融資のバランスを考慮しながら、財務体質の強化と情報開示の充実を図ることが重要です。
実例:成功する融資申請書類の作り方
人材紹介業C社(設立3年目)の事例を見てみましょう。
C社が提供した過去情報は、職種別・クライアント企業別の成約実績分析から始まりました。単に「IT人材の紹介で年間100名成約」というだけでなく、エンジニアが60名、営業職が25名、管理部門が15名といった具合に詳細に分析。さらに成約単価の推移を示し、なぜ高単価案件が増えたのか、その獲得戦略まで説明しました。コンサルタント別の生産性指標も月次で追跡し、一人当たり何名の成約を上げているかを明確にしました。
将来情報としては、すでに契約済みの求人案件リストを作成し、過去の成約率を掛け合わせて成約見込みを算出。新規開拓予定の企業リストも、過去に同規模・同業種の企業でどれくらいの成約率だったかというデータと併せて提示しました。そして、これらを基に向こう6ヶ月の売上予測と資金繰り計画を作成したのです。
特に銀行から評価されたのは、「過去2年間の成約実績から算出した成約率を基にした売上予測」でした。人材紹介業特有のKPIを活用し、返済能力を具体的に示したことが融資承認につながりました。
融資審査でよくある失敗と対策
避けるべき3つの落とし穴
まず気をつけたいのが、実現性の低い事業計画です。「来年は売上倍増」といった過度に楽観的な予測は、かえって信頼性を損ないます。保守的なメインシナリオを基本とし、ベストケースとワーストケースも併せて提示することで、リスク管理ができている企業という印象を与えることができます。
次に、資金使途の不明確さも問題です。「運転資金として3,000万円」だけでは説明不足。仕入資金として1,000万円、人件費として1,500万円、広告宣伝費として500万円など、具体的な使途と金額を明確にすることが重要です。
そして返済計画の具体性不足も失敗の原因になります。どの売上から返済するか、売上が計画を下回った場合はどう対応するか。こうした具体的な返済シナリオを複数準備しておくことが大切です。
融資決定後のアフターフォローで次回融資につなげる
融資が決定したら終わりではありません。むしろ、その後の対応が次回の融資審査に大きく影響します。
まず重要なのは定期的な業績報告です。四半期ごとに計画と実績の差異分析を含めて報告することで、銀行は貴社の事業を継続的に把握できます。良い情報だけでなく、問題が発生した際も早期に相談することで、むしろ信頼関係が深まります。
また、担当者とのコミュニケーションも大切です。決算説明会に招待したり、新商品の発表会に呼んだりと、直接対話の機会を設けることで、書類だけでは伝わらない事業への熱意や将来性を感じてもらえます。
このような継続的な情報提供により、金融機関は貴社の事業を深く理解し、次回の融資審査時にはよりスムーズな対応が期待できるので
本記事では、融資審査に強い決算書と資料作りについて解説しました。
ポイントは、過去情報を詳細な内訳と背景説明で事業実態を明確に示すことです。そして将来情報では適切な借入先選定と実現可能な返済計画が重要です。さらに業界特性を理解し、銀行の「返済可能性」という視点で資料を準備することが成功への近道となります。
Iroae税理士事務所では、成長企業に特化した税務顧問サービスを提供しています。月次決算の早期化支援から、成長を見据えた管理体制の構築までサポートいたします。まずは無料相談で貴社の課題をお聞かせください。