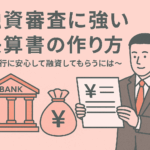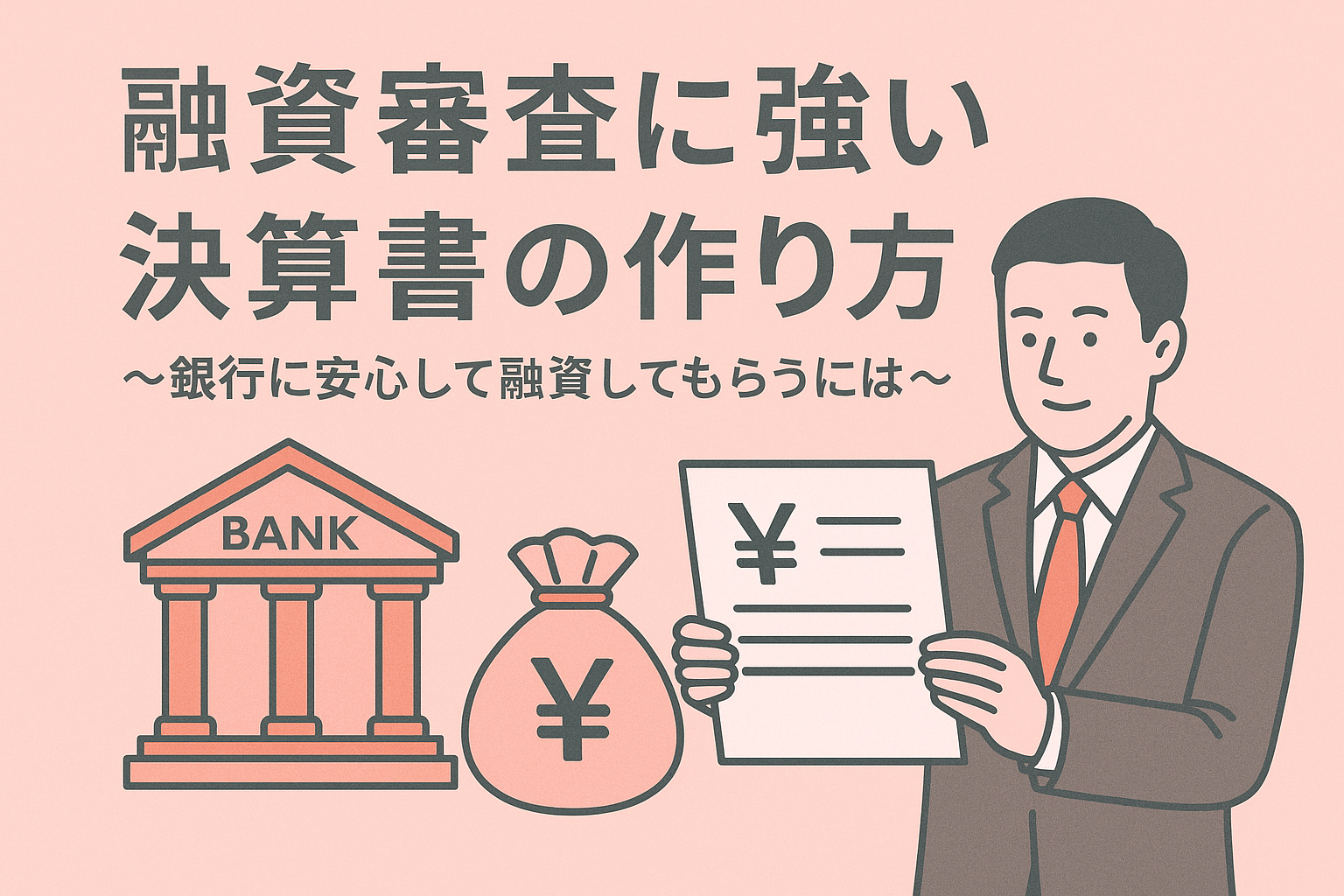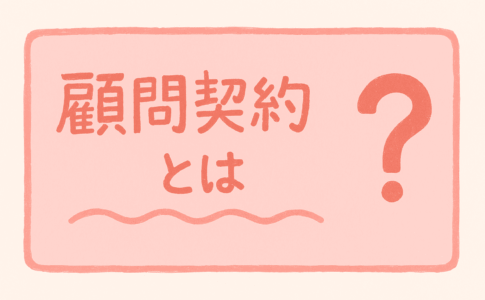スタートアップの経理担当者必見!月次決算が締められない、請求書管理が追いつかない…そんな課題を解決する経理体制の構築方法を解説。成長企業が今すぐ始めるべき仕組み作りとは?
なぜ月次決算が締められないのか?スタートアップ経理の現実
「また今月も月次決算が遅れている…」
多くのスタートアップ経理担当者が抱える共通の悩みです。事業が成長し始めた頃から、この問題は急速に深刻化します。取引先が増え、請求書は月末を過ぎてからバラバラと届き、経費精算は締切後も続々と提出される。結果として、月次決算の締めは翌月20日を過ぎることも珍しくありません。
しかし、この状態を放置すると、資金繰りの把握が遅れ、経営判断のスピードが低下し、最悪の場合は黒字倒産のリスクすら生じます。成長期の企業にとって、タイムリーな財務情報は生命線です。今こそ、場当たり的な処理から脱却し、体系的な経理体制を構築する時期なのです。
月次決算を阻む3つの構造的問題とは
月次決算が締められない背景には、単なる人手不足以上の構造的な問題が存在します。
1. 情報収集の仕組みの欠如 多くのスタートアップでは、請求書の受領や経費精算が「届いたら処理する」という受動的なフローになっています。事業規模が小さいうちは問題になりませんが、取引量が増えると、この方法では情報の取りこぼしが頻発します。
2. 締切概念の未浸透 「月末」という概念が社内で共有されていないケースも多く見られます。営業担当は「売上が上がればいつでもよい」と考え、購買担当は「必要な時に買えばよい」と判断します。この認識のズレが、月次決算の遅延を招きます。
3. 承認フローの未整備 取引が発生してから経理に情報が届くまでの承認フローが確立されていないと、情報の滞留が起こります。特に、部門長の承認待ちで1週間以上かかるケースは要注意です。
これらの問題を解決するには、情報を「待つ」のではなく「取りに行く」能動的な仕組みが必要なのです。
情報収集の仕組み化:3つの基本ステップ
ステップ1:取引の見える化
まず着手すべきは、すべての取引を可視化することです。成長期の企業では、以下の仕組みを導入することを推奨します。
受注管理表の導入
- 営業部門に受注と同時に入力してもらう
- 売上計上予定月を必須項目とする
- 週次で経理部門と共有する
発注管理システムの構築
- 一定金額以上の支出は事前申請制とする
- 発注時点で支払予定月を登録する
- クラウド型の簡易システムでも十分機能する
ステップ2:締切の明確化と周知
「いつまでに何を提出するか」を全社員が理解している状態を作ります。
月次カレンダーの作成と配布
- 営業日ベースで締切を設定(例:月末営業日の3営業日前)
- 部門別の提出物リストを作成
- 全社会議で毎月リマインドする
ステップ3:自動化できる部分の特定
人力に頼らない仕組みも並行して構築します。
API連携の活用
- 銀行口座の入出金データの自動取得
- クレジットカードの利用明細の自動連携
- 請求書発行システムとの連携
これらの仕組みを段階的に導入することで、情報収集の精度とスピードは飛躍的に向上します。
デジタルツールを活用した効率的な体制構築
クラウド会計システムの真の活用法
多くの企業がクラウド会計を導入していますが、その機能の20%程度しか活用できていません。成長企業が最低限活用すべき機能は以下の通りです。
証憑の電子保存機能
- スマートフォンでの領収書撮影
- PDFの請求書の自動取り込み
- タイムスタンプによる証明力の確保
ワークフロー機能
- 経費精算の申請から承認まで
- 支払依頼の電子化
- 承認状況のリアルタイム把握
予実管理機能
- 部門別予算の設定
- 月次での予実差異分析
- アラート機能による異常値の早期発見
情報共有プラットフォームの構築
経理部門だけでなく、全社で財務情報を共有する文化を作ることが重要です。
経営ダッシュボードの作成
- 売上、粗利、固定費の日次推移
- キャッシュフローの見える化
- KPIの自動更新
部門別収支の開示
- 各部門の貢献度を可視化
- コスト意識の醸成
- 予算執行率のリアルタイム共有
これらのツールを適切に組み合わせることで、少人数でも大企業並みの経理体制を構築できます。
実例:IT企業の体制構築事例
A社(SaaS事業、従業員15名)は、事業が急成長する中で月次決算が翌月25日までかかっていました。以下の施策を3ヶ月かけて実施した結果、翌月10日での月次決算締めを実現しました。
実施した施策
- 週次ミーティングの導入
- 営業、開発、管理部門の代表者が参加
- 当月の取引予定を共有
- 未処理案件の洗い出し
- 請求書の電子化推進
- 取引先に電子請求書への切り替えを依頼
- 応じない先には月末3営業日前の送付を要請
- 結果として80%が電子化に対応
- 経費精算ルールの厳格化
- 発生月の翌月5日締切を徹底
- 遅延した場合は翌々月払いとするルールを導入
- 結果として期限内精算率が95%に向上
得られた成果
- 月次決算が翌月10日に短縮
- キャッシュフロー予測の精度が向上
- 経営会議での意思決定スピードが2倍に
この事例から分かるように、仕組み化は一朝一夕には実現しません。しかし、着実に進めることで必ず成果は出ます。
体制構築時の注意点:よくある失敗パターン
完璧主義の罠
「すべての取引を100%把握してから始めよう」という考えは危険です。成長段階では、重要性の原則に基づいて、以下の優先順位で進めることを推奨します。
- 売上の大部分を占める主要取引先
- 継続的に発生する固定費
- その他の取引
システム依存の弊害
最新のシステムを導入すれば解決すると考えがちですが、仕組みとルールが確立していない状態でのシステム導入は失敗に終わります。まずは、Excelベースでも構わないので、業務フローを確立することが先決です。
現場の抵抗への対処
新しいルールの導入には必ず抵抗が生じます。特に営業部門からの「面倒くさい」という声は避けられません。この場合、以下のアプローチが有効です。
- 導入の必要性を数字で示す(決算遅延による機会損失額など)
- 段階的導入で負担を軽減する
- 成功事例を早期に作り、横展開する
まとめ:今すぐ始めるべき3つのアクション
本記事では、成長を見据えた企業の経理体制構築について解説しました。
重要なポイントは以下の3つです。
- 情報を「待つ」から「取りに行く」体制への転換
- 締切と提出物の明確化による全社的な意識改革
- デジタルツールを活用した業務の効率化と可視化
成長段階や業種により最適な対策は異なります。
Iroae税理士事務所では、成長企業に特化した税務顧問サービスを提供しています。月次決算の早期化支援から、成長を見据えた管理体制の構築までサポートいたします。まずは無料相談で貴社の課題をお聞かせください。