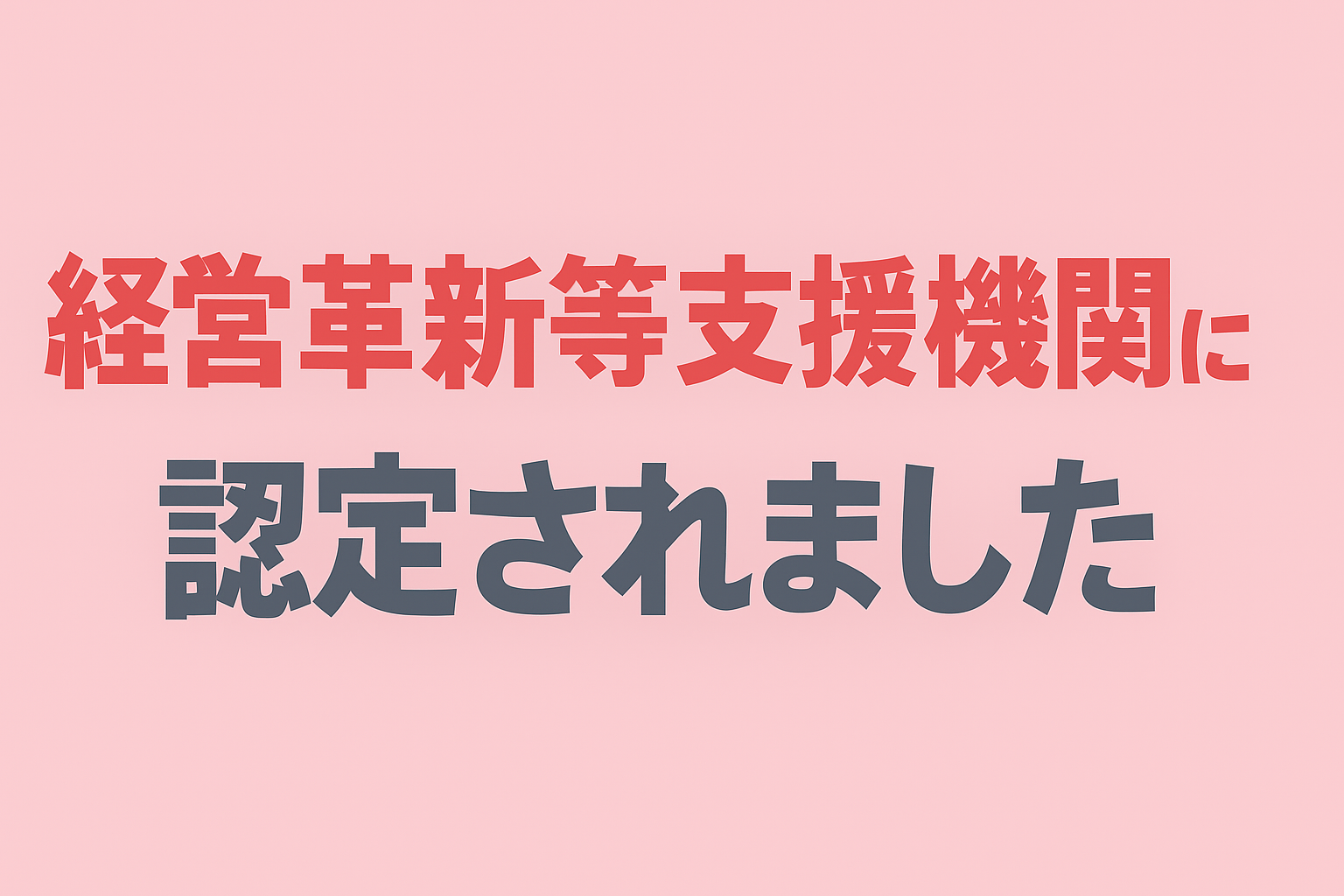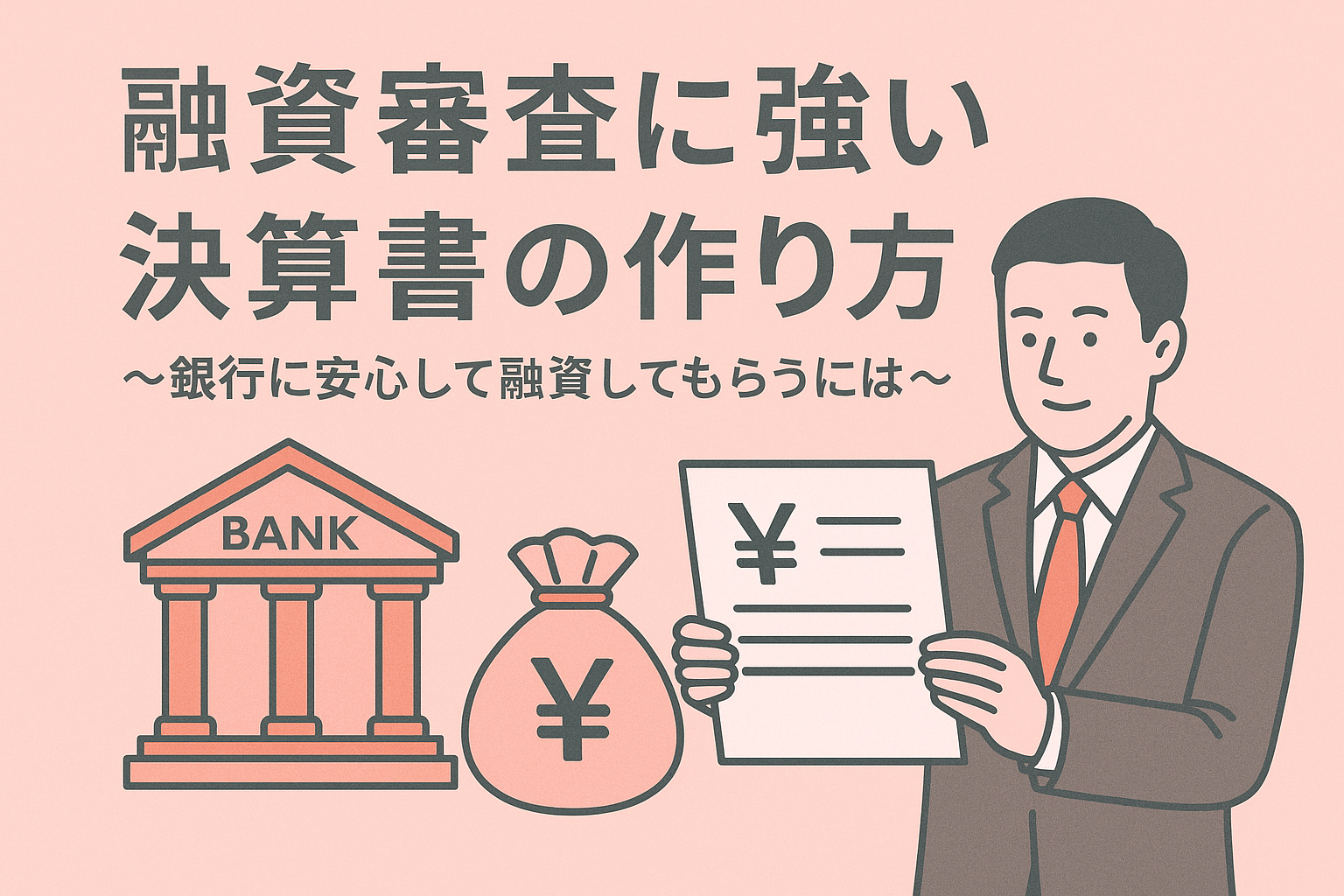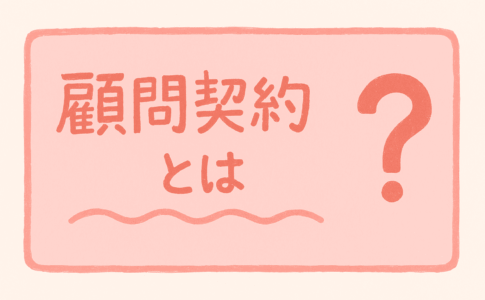売上1億円達成に向けて本当に必要な税務管理体制とはなんでしょうか。業種・取引形態別の実務的なポイント、最小限のルールで最大の効果を出す方法を解説します。形式的な体制構築ではなく、現場で機能する仕組みづくりのガイドです。
必要な管理体制のレベルとは
先日、2つの企業から立て続けに相談を受けました。どちらも売上は7000万円前後でしたが、抱えている問題は正反対でした。
1社目は部品商社で、取引先は10社程度。月の請求書は15枚ほどで、社長と奥様の2人で十分に経理を回していました。ところが2社目のネット通販企業は、1日の注文が100件を超え、月間の取引は3000件以上。経理担当者が毎日残業しても処理が追いつかず、売掛金の管理もできていない状態でした。
この2社を見ても分かるように、売上規模だけで必要な管理体制を判断することはできません。取引の数、複雑さ、業種特性によって、必要な体制は全く変わってくるのです。売上3億円でもシンプルな管理で回っている企業もあれば、売上5000万円でも複雑な管理体制が必要な企業もあります。重要なのは、自社の実態を正確に把握することです。
まず確認すべき3つの基本要素
自社の取引パターンを把握する
経理の体制で一番重要なのは、自社がどんな商売をしているかを正確に理解することです。業種によって重視すべき管理ポイントは全く異なります。
例えば、飲食店なら毎日の現金管理と仕入れの原価管理が中心になります。一方、ITサービス業なら、プロジェクトごとの進捗管理と売上計上のタイミングが重要です。建設業では工事の進行基準と原価の積み上げ、小売業では在庫回転率と粗利管理というように、それぞれの業種特性に応じた管理体制を構築する必要があります。
同じ売上1億円でも、必要な経理体制は業種によってこれほど違うのです。他社の事例を参考にする際も、同業他社の事例を重視すべきでしょう。
月間取引件数と金額の分布
売上1億円といっても、その中身は企業によって全く異なります。月に1000万円の取引を10件こなす企業と、10万円の取引を1000件こなす企業では、必要な管理体制が全く違ってきます。
前者なら正直なところ、社長が手帳にメモしておくだけでも管理できてしまいます。しかし後者の場合は、何らかのシステム化を考えないと、処理に追われて本業に支障が出てしまうでしょう。
必要になる組織的ルール
売上が1億円に近づくと、今まで社長の頭の中だけで管理していたことを、組織として管理する必要が出てきます。これは避けて通れない成長の痛みです。
売上5000万円までは、社長が全ての取引を把握し、重要な判断を一人で下すことができました。しかし1億円を超えると、取引量も従業員数も増え、社長一人では管理しきれなくなります。ここで必要になるのが、誰が見ても分かる明文化されたルールです。
例えば、今まで「高額な支払いは社長に相談」だったものを、「10万円以上は事前申請、30万円以上は稟議書が必要」といった具体的な基準に落とし込む。こうした組織的なルール作りが、売上1億円企業には不可欠になってきます。
業種別・取引形態別の実務的な税務管理ポイント
EC・ネット通販事業の場合
ECサイトを運営している企業の経理で一番の悩みは、プラットフォームごとに売上データの形式が違うことです。Amazon、楽天、自社サイト、それぞれから出てくるデータをどう統合するか。
あるECの企業では、最初は全てのデータを手作業でExcelに転記していました。しかし、売上が月3000万円を超えたあたりで限界が来て、結局各プラットフォームのデータをCSVで吐き出し、Excelのマクロで集計する仕組みを作りました。完璧ではありませんが、作業時間が10分の1になったそうです。
もう一つ重要なのが、在庫と売上の突合せです。月に1回でいいので、実際の在庫数と帳簿上の在庫が合っているかチェックする。これをサボると、気づいたら在庫が合わなくなっていて、決算で大慌てすることになります。
受託開発・コンサルティング業の場合
この業種で最も悩ましいのが、売上をいつ計上するかという問題です。プロジェクトが3ヶ月かかる場合、完成時に計上するのか、それとも進行に応じて按分するのか。収益を計上する基準を明確に決めておくことが必要です。基本的には一度決めたルールを頻繁に更新することは、利益操作と疑われてしまう可能性があるため一度決めたルールは運用を継続することが前提です。
100万円未満の案件は検収時に一括計上、100万円以上で工期3ヶ月以上の案件は進行基準で毎月計上する。シンプルですが、これで税務調査でも問題になったことはないそうです。
また、外注費の管理も重要です。フリーランスのエンジニアに仕事を頼むことが多い業界なので、発注時点で予算を確保しておかないと、プロジェクトが赤字になってから気づくということになりかねません。
卸売業の場合
卸売業では、在庫管理が経理の肝になります。ただし、全ての在庫を同じように管理する必要はありません。売上の8割を占める主力商品だけをしっかり管理して、残りはざっくりでも構わないのです。
ある金属加工業の会社では、主要な材料10品目だけは毎日在庫をチェックし、それ以外の細かい部品類は月1回の棚卸で確認するという方法を取っています。完璧ではありませんが、実務的にはこれで十分回っているとのことでした。
最小限の投資で最大の効果を出す実践的アプローチ
業務フローの理解から始める効率化
「ペーパーレス化しなければ」「クラウド会計を導入しなければ」と焦る前に、まず自社の業務フローを理解することが大切です。実は多くの企業が、自社の経理業務の流れを正確に把握できていません。
まず、現在の業務の流れを書き出してみましょう。請求書が届いてから支払いまで、どんな手順を踏んでいるか。売上計上から入金確認まで、誰がどのタイミングで何をしているか。これを可視化するだけで、無駄な作業や二重チェックが見えてきます。
次に、それぞれの作業について「本当にシステム化が必要か」を検討します。例えば、月10件しかない経費精算なら、Excelの管理表で十分かもしれません。一方、毎日100件の注文がある場合は、受注管理システムの導入を検討すべきでしょう。
フォーマットの統一も重要です。請求書、見積書、発注書などの書式がバラバラだと、処理に時間がかかります。まずはExcelやGoogleスプレッドシートで統一フォーマットを作り、それを全社で使うようにする。これだけでも業務効率は大幅に改善します。
月次決算は経営判断のためのツール
月次決算は、税務署に提出するためのものではありません。経営判断のための情報を得るためのものです。
そのため、完璧を求める必要はありません。売上、粗利、現金残高、この3つの数字が把握できれば、経営判断には十分です。細かい経費の按分や、1円単位の調整は後回しでも構いません。
重要なのは、毎月同じタイミングで数字が出ることです。10日締めと決めたら、必ず10日に数字を出す。精度は70点でも、タイミングが一定なら、前月比較や前年比較ができるようになります。
よくある失敗と対策
自社に合わないシステムの導入
システム導入で最も多い失敗が、自社の業務実態に合わないシステムを選んでしまうことです。従業員10名の広告代理店が、「将来の成長を見越して」と大手企業向けのワークフローシステムを導入したケースもあります。承認ルートの設定が複雑すぎて、簡単な経費精算に5段階の承認が必要になり、かえって業務が煩雑になってしまいました。
システムを選ぶ際は、以下の点を必ず確認してください。まず、同業他社での導入実績があるか。業種特有の処理に対応しているか。次に、現在の業務量に対して機能が過剰でないか。将来の拡張性はあるか。そして、担当者のITリテラシーに合っているか。サポート体制は充実しているか。
特に重要なのは、無料トライアルで実際の業務データを使って検証することです。デモ画面だけでは分からない使い勝手の問題が、実際に使ってみると見えてきます。
社内ルールの形骸化
立派な経理規程を作っても、誰も読まなければ意味がありません。私がおすすめするのは、A4用紙1枚に収まる「経理の基本ルール」を作ることです。
例えば「5万円以上の支払いは事前にSlackで相談」「請求書は月末締めの翌月10日発行」「領収書は1週間以内に提出」といった、本当に守ってほしいことだけを書く。これだけでも、経理業務はずいぶん楽になります。
大切なのは、売上規模に惑わされず、自社の取引実態に合った仕組みを作ることです。完璧な体制を最初から作ろうとせず、まずは最低限のルールを決めて、それを確実に実行する。高額なシステムに飛びつく前に、今あるツールを使い倒す。こうした地道な積み重ねが、結果的に最も効率的な税務管理体制につながります。
成長段階や業種により最適な対策は異なりますので、具体的な実施にあたっては、貴社の状況に精通した税理士にご相談されることをお勧めします。
Iroae税理士事務所では、通常の税務顧問に加えて、成長企業に特化したバックオフィス体制の構築支援サービスを提供しています。まずは無料相談で貴社の課題をお聞かせください。